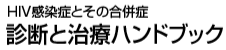HIV感染症の診断
Last updated: 2022-09-29
HIV検査を行う前には必ず患者本人に説明し同意を得る必要がある。ただし、意識障害などにより本人からの同意取得が困難な場合には「医師の判断で」実施する事が認められている。小児患者に対しては保護者の同意を得て行う。
HIV検査は、通常①スクリーニング検査、②確認検査の順番で行われ、確認検査の陽性をもってHIV感染症の確定診断を行う。
HIVスクリーニング検査
日本では、第4世代のHIVスクリーニング検査が広く用いられている(表1)。第4世代検査ではHIV抗体とHIV-1抗原を同時に検査するため、window period(HIV感染が成立してから検査が陽性となるまでの期間)は最短17日と短縮しているが、感染初期には偽陰性となりうる。このため、臨床的に急性HIV感染症を疑う場合には、間隔をおいて再検査を行うか、HIV-1 RNA-PCR法による診断確定を行う必要がある(2022年4月現在、急性HIV感染症の診断を目的としたHIV-1 RNA-PCR検査は、保険が適応しない)。一方で、第4世代の抗原検出系の感度は血中ウイルス量で10万コピー/mL程度と必ずしも高くないため、急性期の経過中に見られるウイルス量減少により、スクリーニング検査が一時的に再陰性化するsecond windowが見られたという報告もなされている。
HIVスクリーニング検査は常に偽陽性の可能性があり、有病率が低い集団(特に日本の妊婦)で検査を行う際に特に大きな問題となる。スクリーニング検査陽性の段階で結果説明を行う場合には、必ず偽陽性の可能性を念頭に置く必要がある。
表1 HIV感染症の診断に用いられる各検査の特徴
確認検査
2008年版のガイドライン[1]では、確認検査として「ウェスタンブロット法」と「核酸増幅検査法(RT-PCRなど)」が推奨されていたが、ウェスタンブロット法からイムノクロマト法を用いた新たな抗体確認検査法への世界的な移行を受けて、2020年版のガイドライン[2]では「新規のHIV-1/2抗体確認検査法(Geenius HIV-1/2キットⓇ)」と「核酸増幅検査法」の同時施行が推奨されている(図1)。
図1 診療におけるHIV-1/2感染症の診断のためのフローチャート2020
感染症法に基づく届け出
HIV感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において五類感染症(全数把握)と規定されており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所長を通じて都道府県知事に届出を行う必要がある[4]。
また、発生届が提出されたHIV感染者にその後病状の変化(エイズ発症・死亡)がみられた場合、患者さんへの説明と同意のもと、診断した医師は任意に規定の書式を用いて届出を行うこととされている。
HIV検査結果の告知
HIV検査結果は、その結果に関わらず、検査を受けた本人に説明するのが原則である。結果の告知は、感染者がHIV感染症と初めて向き合う瞬間であり、疾患イメージの形成に大きな影響を与える。正しく告知することによって感染者自身の誤解や偏見を取り除き、生涯にわたる治療に取り組む原動力を与えることができる。HIV検査結果告知にあたっては、プライバシーに配慮した環境が用意されていることを確認し、以下の情報を伝える。
・現在の状態:「HIVスクリーニング検査陽性=確認のための追加検査が必要」なのか「HIVに感染している」のか
・HIV感染症には有効な治療法が存在し、合併症がなければ長期生存が期待できること
・早期に専門家の診察を受けることが望ましいこと
・日常生活では他者に感染させることはないこと
・電話相談窓口やカウンセリング体制が存在すること
・治療費用について様々な支援制度が存在すること
告知の時点で落ち着いているように見えても、時間が経ってから疑問や混乱、不安が生じる可能性がある。衝動的に大きな決断(仕事や学校を辞める、見境のなくカミングアウトするなど)をしないようアドバイスする。
参考)東京都保健福祉局 感染告知支援資料「たんぽぽ」https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/koho/kansen.files/tanpopo.pdf
参考文献
1)診療におけるHIV-1/2感染症の診断 ガイドライン2008(日本エイズ学会・日本臨床検査医学会 標準推奨法). 日本エイズ学会誌 11(1):70-72, 2009.
2)診療におけるHIV-1/2感染症の診断ガイドライン2020版(日本エイズ学会・日本臨床検査医学会 標準推奨法)(https://jaids.jp/wpsystem/wp-content/uploads/2021/01/guideline2020.pdf)(2022年4月15日最終アクセス)
3)Patel P, et al. Detecting acute human immunodeficiency virus infection using 3 different screening immunoassays and nucleic acid amplification testing for human immunodeficiency virus RNA, 2006-2008. Arch Intern Med 2010;170(1):66-74.
4) 感染症法に基づく医師の届出のお願い 後天性免疫不全症候群(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-07.html (2022年4月15日最終アクセス)
著作権について
当サイト内のコンテンツ(文章・資料・画像・音声等)の著作権は、特に記載のない限り、国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センターまたは第三者が保有します。営利、非営利を問わず、当サイトの内容を許可なく複製、転載、販売などに二次利用することを禁じます。